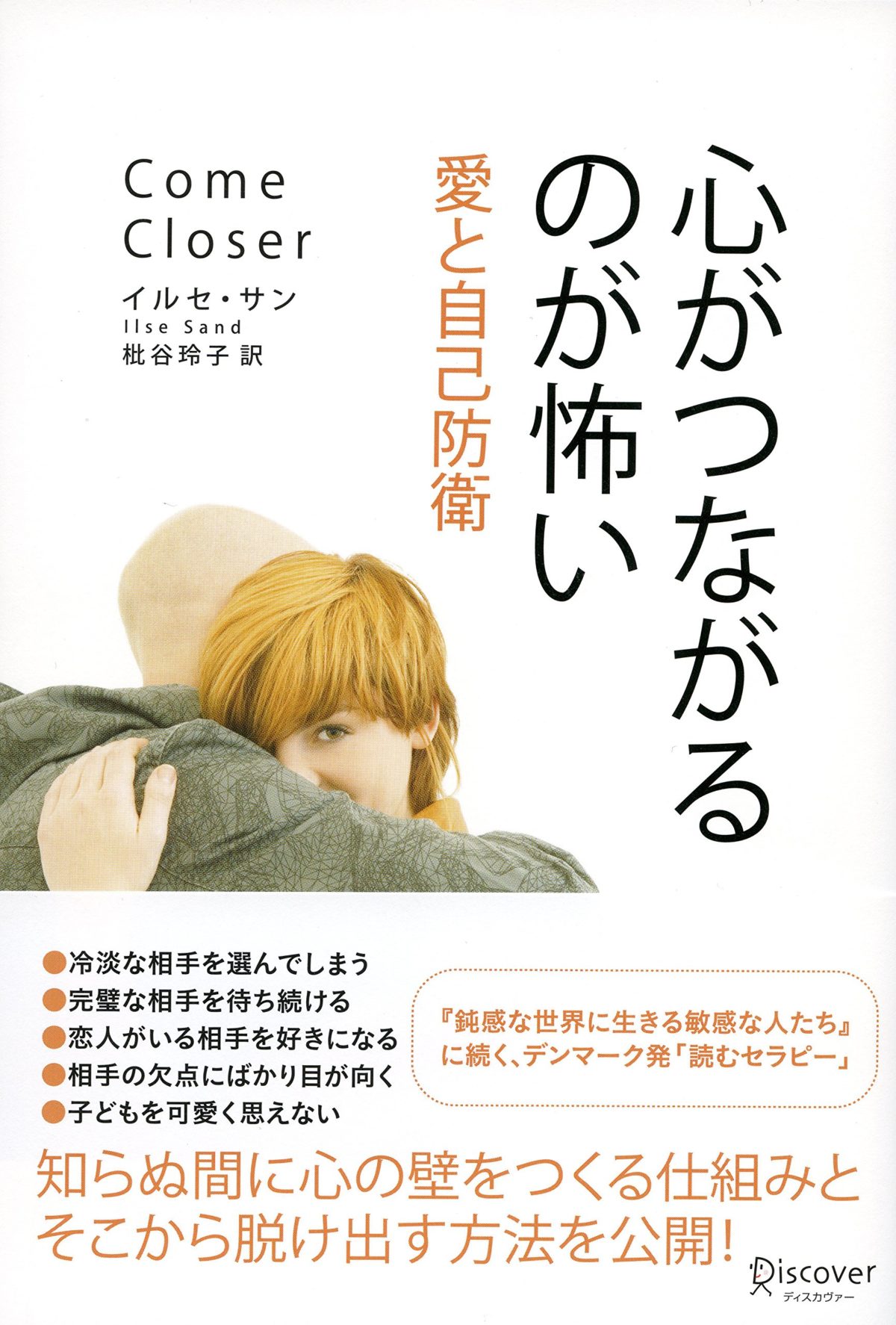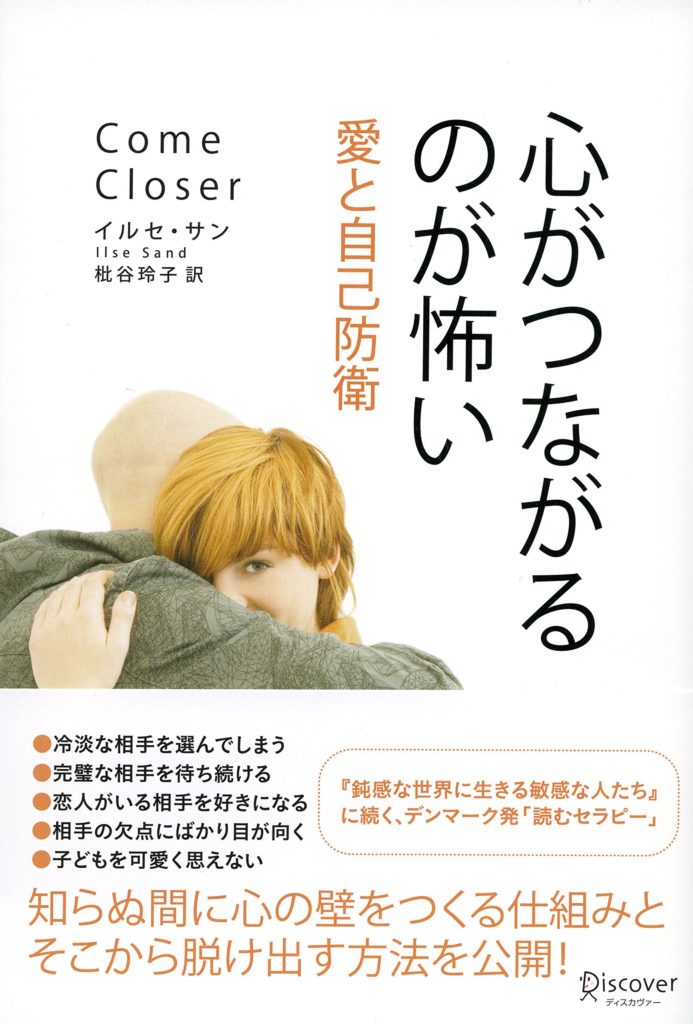独白するだけのゴリラになりたい。あと転職したい。
今更ながら映画「娼年」を観た。
性行為における深淵を垣間見たような気がしたので、セックスについて真剣に考えてみた。
セックスは暴力的なまでに自己開示を迫る行為だと思っている。セックスにおける「愛」の要不要は置いて話を進める。
物理的に衣服を纏っていないという自己開示だけでなく、裸体を見せても良いと心を開くところまで含めての話だ。
世間がどう思ているかは知らないが、セックスはあまりポジティブに語られることがない。
性行為が子どもに秘匿されているために開けっ広げに語ることが出来ない風潮も関与しているかもしれないが、個人的にはセックスが恐ろしい行為だからだと思う。
ところが、何故恐ろしいと思うのかを深堀して考えたことがなかったので、ヒントになりそうな本を適当に買ってみた。
上述したように、セックスの恐ろしさは自己開示の強制力だと考えている。
だから、なるべくこの自己開示の強制力の恐ろしさについて書いてありそうなタイトルの本を探した。
それが、デンマークで牧師をしながら心理療法士やセラピストとして多方面で活動をしているイルセ・サン著の「心がつながるのが怖い」という本だ。
心がつながるのが怖い
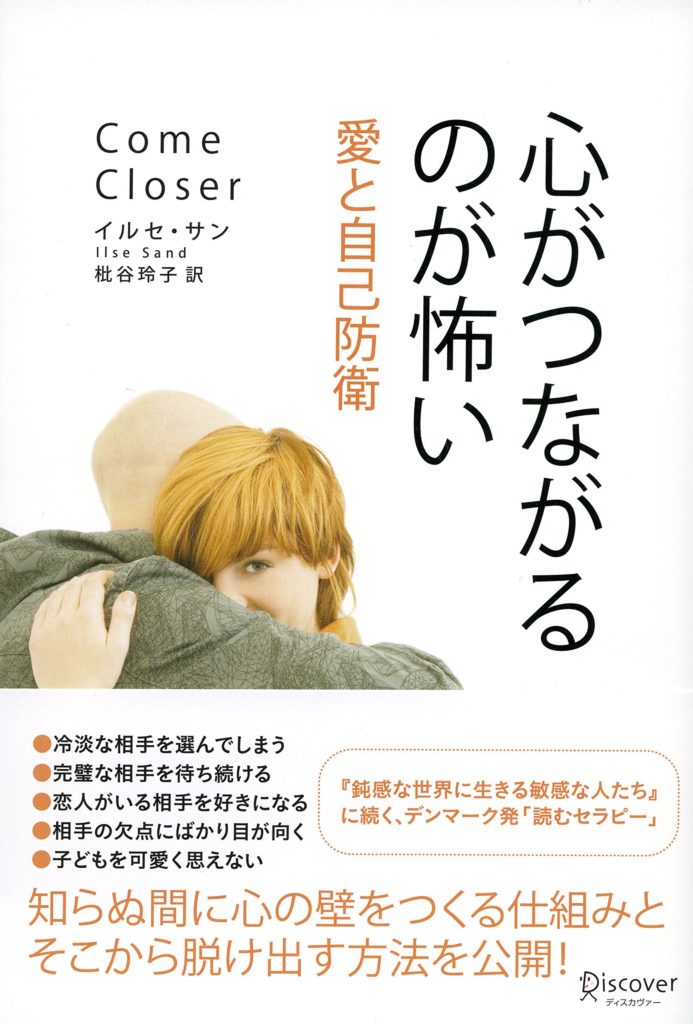
結論から言うと、この本はセックスについての考察を深めるのに有効ではなかった。
しかし、自分に新しい考え方を与えたくれたので、本日はタイトル詐欺になるが、この本の内容について記していく。
本書は、自分の痛みや悲しみから目を背けるために、他人と対等な関係を築くのが難しいと感じている人のための読むセラピーであるらしい。
らしいというのは、帯にそう書いてあるからだ。
著者は、こういう症状に悩まされている人の多くは幼少期の親との関係が原因であると述べている。
親の存在が大人になってからの精神形成にも大いに影響を与えるという観点はユングっぽいな、と思ったが、調べてみると著者はユングに関する修士論文を執筆した過去があった。
基本的にテーマは「自己防衛」についてだ。
本人も理由はわからないが、他人が近づいたり愛情を表現してくれるとその関係を遠ざけるような言動をとってしまう。これは、幼少期に形成された習慣で、自己防衛である、という観点から原因と対策について書かれている。
この辺りについては特に思うこともなかったので気になるのであれば自分で本を買ってみるといい。「読むセラピー」というだけあって、特定の人には確かに効果がありそうだった。
感情は重なり合って互いを隠している
前の記事にも書いたが、あらゆる感情の中で最もエネルギーが高い(カロリーが高いと言ったほうが適切かも…)のは怒りだ。
イルセ・サンは感情を完全に理解するには体・衝動・頭の3つの面においての意識する必要がある。
例えば恐怖という感情を例にとってみる。
●体:震えるのを感じる。
●衝動:叫びながら走って逃げたい衝動を感じる。
●頭:恐怖していると頭で知る。
喜びなら、
●体:体の中に踊りたくなる感覚がする。
●衝動:突然歌いだしたくなるような衝動が湧く。
●頭:自分が喜んでいるのを頭で知る。
お粗末な説明だが、そのままの引用なので勘弁してほしい…
ここで注目して欲しいのは衝動についてだが、自分に限って述べるのであれば怒りの衝動はその他の感情を圧倒的に上回る。
なにせ強すぎる怒りの衝動のあまり、超サイヤ人になるサイヤ人まで出てくるの始末である。怒りで黒髪から金髪に変わるのだからその衝動力たるや筆舌に尽くせない。
 怒りの衝動で超サイヤ人になった孫悟空さん(本名カカロットさん)
怒りの衝動で超サイヤ人になった孫悟空さん(本名カカロットさん)
 こちらも怒りの衝動で超サイヤ人になったベジータさん
こちらも怒りの衝動で超サイヤ人になったベジータさん
怒りが最もカロリーの高い感情であることは今も疑っていないが、イルセ・サンの著書によると感情というのは複数の感情が重なりあい、ある感情が別の感情を覆い隠している場合があるという。
そして怒りはその重なりの一番上の層にある。
何故怒りが一番上の層にあるのかについても説明がある。
曰く、怒りとは内と外の両方から効率的に身を守る戦略なのだ。
怒りにより、他人を追い払うことで外部から自分を守り、一番上の層にある怒りを強く感じることで、その下の層にある無気力や悲しみなどの他の感情を感じないようにする自らを内側からも守る。
怒りはそのカロリーの高さから、消化するまでに他の繊細な感情を感じにくくする。
面白かったのはこの後だ。
著者のスタンスは、ひとは潜在的に痛みを避けたがるので、自らが傷つかないように自己防衛の戦略(他人との関係に距離を置く)をとる。この自己防衛戦略のちからが弱まると、多くの場合ひとは怒り(もしくは不安)の感情を表す。
そして、その下の層には悲しみや渇望があるとしている。
セラピストとして活躍する著者は、この悲しみや渇望に自ら気付き、表現することで、他者に近づいてつながるという大きな体験をさせることを目標に相手と向き合っている。
つまり、自己防衛の戦略として他人を遠ざけるひとは、自信が気が付かないうちに悲しみをブロックし、体験すべき悲しみを自分の性格に統合しないように働きかけている。
だから、悲しみと向き合えるように働きかけるのだ。
悲しみを感じるのが傷を癒すプロセスなのだ!
インサイドヘッドとの共通点
この悲しみについての認識は、自分に映画インサイドヘッドを思い出させた。
2015年に上映されたディズニーピクサー映画で、11歳の少女ライリーの持つ5つの感情(ヨロコビ、ビビリ、カナシミ、イカリ、ムカムカ)についての物語だ。

本作は、多くの神経学者からアドバイスをもらいながら5年の年月をかけて完成させた力作であり、ひとの感情の働きや仕組みについてユーモアたっぷりに描いている。
例えば、作中で考えの列車に積まれた箱が倒れて、中のカードが出てきてしまうシーン。
「”意見”と”事実”のカードがごちゃごちゃ!」
「平気、いつものことさ」
これなどは思わず笑ってしまうが、なるほどと考えさせられる上質なユーモアだ。
5つの感情の中で主に司令官を務めるヨロコビは、ライリーが暗い感情を抱かないようにとカナシミの干渉をなるべく回避する。
わけあってヨロコビとカナシミは2人で行動を共にするのだが、ここでも行動の主導権を握るのはヨロコビだ。
ヨロコビは行動的で、常に明るく場の空気を楽しくさせるために振る舞う。
道中、2人はライリーが昔遊んでいたイマジナリーフレンド(幼少期に子どもが作る想像上の友達)であるビンボンと出会い、3人で冒険することになる。
途中でビンボンが、昔はいつも遊んでいたライリーが自分のことを忘れ始めていることにショックを受けて足を止めてしますシーンがある。
ヨロコビは大丈夫、他にも楽しいことがあると励まして前進を促すのだが、ビンボンはすっかり落ち込んでしまって動けない。
ここで初めてカナシミがポジティブな働きをする。
ポジティブな働きと言っても、カナシミの言動は徹頭徹尾ネガティブな感情とされる悲しみの表現でしかないのだが、悲しみという感情がポジティブに描写されるのだ。
カナシミは落ち込むビンボンに寄り添い、一緒に悲しんだのだ。
ビンボンはカナシミと抱き合って泣くと、「もう大丈夫」と立ち上がり再び前進する。
まさに悲しみを感じることが癒しのプロセスであることがここに描かれている。
インサイドヘッドは、ヨロコビがライリーの幸せを願うあまりに、カナシミを厄介者として扱い、遠ざけていたが、そのカナシミの重要性に気が付くという王道のストーリーだ。
これは、イルセ・サンの本の内容をそのまま表している。
彼は喜びと悲しみはとても近い感情だと見解を述べているが、これに当てはまるような描写も本作の中で見られる。
ヨロコビが、ライリーが大好きなアイスホッケーの試合に勝利して仲間たちと喜んでいる思い出を見ていた時。
喜びを仲間と分かち合う前に、別の試合でライリーが決勝点をいれることができずに落ち込んでいる悲しみの思い出があることに気付く。
悲しむライリーに両親が寄り添って彼女を励ますのだ。その思い出を見てヨロコビはカナシミがどれほどライリーにとって大切な感情なのかを認識する。
「カナシミ…ママもパパもチーム仲間も、みんなが励ました…カナシミのために」
カナシミは、傷を癒し次の喜びの感情をより高める役割を担っている。悲しみから、喜びが生まれるのだ。
悲しいという感情が持つ特異性
インサイドヘッドでは、5つの感情たちの中でカナシミだけが他の感情の思い出を自分の色に染めるちからを持っている。
それ故に、ヨロコビはカナシミの接触を避けようとするのだが、何故カナシミだけがこのような力を持っているのだろうか。
作中で、悲しみが他者に寄りそうことで癒しの効果を発揮する描写が何度も繰り返される。
つまり、カナシミは寄り添いと共感に秀でていることが強調されているのだ。
この特性こそが、他の思い出を自分の色に染める力に表れているのだと思う。
イルセ・サンの言うように、感情がいくつもの層で覆われているとしたら、我々は日々の生活の中で自らのカナシミの声に気付いていないのかもしれない。
他人に対して深い共感を持つ時、思い返せばそれは相手の悲しみに共感していることが多い。
学生時代の知人の女子が、彼氏にいわゆるヤリ捨てをされたと憤慨していたことがある。
最初、彼女の怒りは真っ当なものだと思っていたし、自分も彼女の彼氏に不快な感情を抱いた。
しかし、話をしていくうちに彼女はとうとうポロポロと泣き出して「悔しい、悲しい」と漏らした。
涙を流す彼女を見て、自分も彼女の気持ちに同調して泣きそうになった。
当時は、何故自分は彼女の痛みを理解できたのかわからなかったが、あれは自分を大切に扱ってくれなかったことに対する彼女の悲しみに共感していたのだろう。
以上を踏まえると、悲しみは優しさにも似ている。
他者に共感して寄り添う、こう書けばそれはまさしく優しさのことではないか。
やさしくなりたい。カナシミの声にもっと耳を傾けよう。思わぬところで結局セラピーを受けたようになってしまった。
では、また。